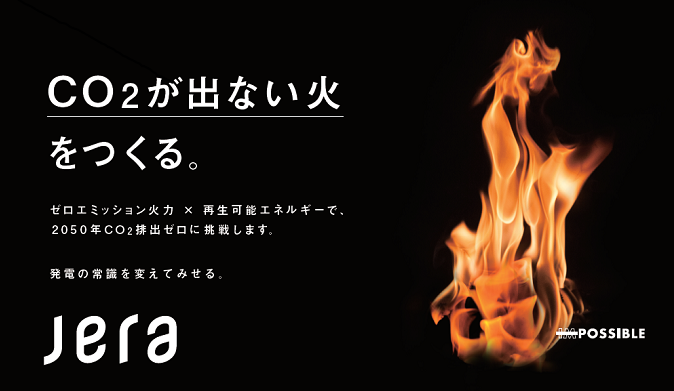「さよならTポイント」、国内最古参のポイントプログラム「Tポイント」が消滅し、三井住友グループが手がける「Vポイント」に統合されました。
「Tポイントはお持ちですか」、Tポイントが登場してポイントを意識するようになったことを思い出します。時代を先取りした新しいサービスといっていいのでしょう。
Tポイントの会員データ分析から企業は何を知るのか - ZDNET Japan
個人データが容易に集まるようになり、ビッグデータ活用の先駆けであったといってもいいのでしょう。それによってマーケティングが変わり、消費スタイルを変えていったといってもよさそうです。
メディアの注目の的であった「蔦屋書店」も当時の勢いはなくなってしまったようです。
「さよならTポイント」、衰退の背景に屋台骨の難題 TSUTAYA不振に「挽回策」の蔦屋書店も拡大せず | ゲーム・エンタメ | 東洋経済オンライン
隆盛を誇ったTポイントも、楽天や通信キャリアのポイントサービスに駆逐され、今に至ります。お膝元で上手くデータ活用できなかったということなのでしょうか。
一方で、Vポイントに統合されたことで新たなポイント経済圏が誕生し、各社の囲い込み競争がより一層激しくなるのではないかとも言われます。
「青と黄色のVポイント」で変わる事、変わらない事 さらに競争が激化する「共通ポイント」サービス | 金融業界 | 東洋経済オンライン
そのVポイントが、SBI 証券のクレカ積立サービスのポイント付与条件を大幅に引き下げ、改悪と利用者の不平を買う事態もおきているようです。
「このタイミングでのポイント付与条件の改悪は、商業道徳上いかがなものか」。
新NISA特需の分捕り合戦を続ける金融業界。個人投資家にとって、銀行口座や証券口座からの引き落としと比べてポイント付与などの魅力があるクレカ積立は人気を集め、金融機関にとっても主戦場となった。(出所:日経ビジネス)
SBI・三井住友、新NISAのクレカ積立「改悪」 かすむ顧客本位:日経ビジネス電子版
楽天証券が楽天ポイントを武器にNISA客の囲い込みを拡大させたことで、血で血を洗うような激しい競争になったようです。ポイント付与率の高さを競い、一方で体力をすり減らす、無謀な戦さのようです。レッドオーシャンはさけるべきと知りながらも、無理を承知で突き進んでしまうというところなのでしょうか。ポイント経済圏も曲がり角にあるように感じます。そろそろ斬新なアイデアによる変化があってもよそさそうな気がします。
楽天が傘下にある決済アプリを再編するそうです。乱立していたアプリを再編し、モバイル事業での躓きから反転攻勢に出るといいます。
楽天グループ、乱立アプリ再編 狙うはスマホ決済「楽天ペイ」誘導 - 日本経済新聞
「フィンテックサービスとの連携を加速し、AI 人工知能を使って次世代アプリにする」
スマートフォン決済「楽天ペイ」のアプリに「楽天ポイント」、電子マネー「楽天Edy」の機能を集約、ポイント利用にとどまっているユーザーに決済サービスを活用してもらうといいます。

効率よくポイ活をしようと思ったら、いずれかの共通ポイントに狙いを定め、日々の暮らしの買い物やサービスの利用を、そのポイント経済圏の中でやりくりするのがいい。とはいえあまり熱心になり過ぎると、わざわざポイント加盟店まで行って購入したり、キャンペーン期間中にまとめ買いしたりと、ポイント重視の行動になってしまいがちだ。(出所:東洋経済オンライン)
良かれと思ったのでしょうが、グループ内に色々なサービスが乱立するようでは非効率と断じても過言ではないような気がします。いくら役立つサービスだったとしても、こんな状態では選択に悩み、場合によってはそのサービスに縛られてかえって不便なことになりそうです。
それはサービスを開発する企業においても同じで効率が悪すぎて生産性を悪化させることになってはいるような気もします。今あるサービスをより意味あるものへと変えていく時ではないでしょうか。
「参考文書」
「楽天ペイ」「楽天ポイントカード」「楽天Edy」アプリを統合 “史上最大級のキャンペーン”も実施(1/2 ページ) - ITmedia Mobile



![マネジメント[エッセンシャル版] マネジメント[エッセンシャル版]](https://m.media-amazon.com/images/I/41UGWMZuQRL._SL500_.jpg)